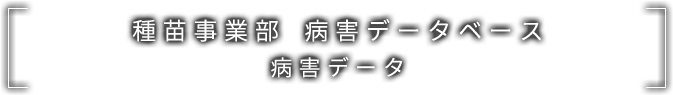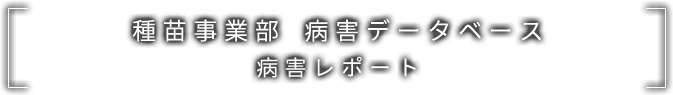ホウレンソウ萎凋病
発生の生態
発生の原因
- ホウレンソウ萎凋病はかび(フザリウム属菌)の一種、Fusarium oxysporum f.sp. spinaciae(フザリウム・オキシスポラム・分化型・スピナシアエ)が原因でおこる病気です。
- このかびは種特異性があってホウレンソウに強い病原性を示します。ダイコン(萎黄病)、キャベツ(萎黄病)、カブ(萎黄病)、ネギ(萎凋病)などには病気を起こすことはありません。
- アカザ、シロザ、サナエタデ、シソ、コイヌガラシなどの根の周りに本病原菌が存在していることもあります。これらの雑草類が畑やその周辺に生育しているときは畑が汚染されやすい心配があります。
病徴
- この病気は本葉展開期の幼苗期ころから収穫期間近まで発生します。
- 幼苗期に発生すると初め子葉がしおれてのちに枯死します。
- 本葉4~6枚ころより収穫期にかけて発生する場合は、下葉の黄化やしおれがみられ、しだいに新しい葉に進展します。このような株は生育不良となりやがて枯死します。
- 葉のしおれた株の根をみると、主根や側根の先端部分や側根の付け根のあたりが黒褐色~茶褐色に変色し、根内部の道管部が黒く褐変しています。病状が激しいと被害根は白色のかび(病原菌)でおおわれています。

伝染方法
- この病気は種子伝染や土壌伝染します。
- 被害残渣中の菌糸や胞子、またそれらから作られた耐久体(厚膜胞子)が伝染源となり、土壌中や種子中で長期間生存します。
- ホウレンソウが播種されるとその生育に伴い土中や被害残渣中で生き延びた厚膜胞子は発芽して根から侵入し、道管内で増殖します。
発生条件
- 夏期から初秋にかけて高温下(25℃~28℃)における露地栽培、雨除け栽培やハウス栽培で多く発生します。地温が15℃以下では発病は少なく、また33℃を越すと発病は急に低下します。
- 黄褐色軽埴土、ホウレンソウの連作年数が多い土壌、水田跡地より畑地土壌では発病が助長されます。
- 土壌水分の乾湿が繰り返されると発病が助長されます。
防除のポイント
耕種的防除
- 健全種子か消毒済み種子を使用してください。
- 発病の激しい株は早期に抜き取り、圃場衛生に努めましょう。
- アカザ、シロザ、サナエタデ、シソ、コイヌガラシなどの雑草が病原菌を保菌していることがあるので除草に努めましょう。
- 発病圃場からの土壌の持ち込みは、本病の発生や被害を増大する危険性があるので、機械、作業着、長靴などに付着した土壌はよく水洗し、汚染土を持ち込まないよう心掛けましょう。
- 雨除け栽培やハウス栽培では灌水に注意し、乾湿条件が繰り返されないよう注意しましょう。
薬剤的防除
- 最新の登録農薬を確認し、使用法に従い正しく使用しましょう。
このページに掲載のイラスト・写真・文章の無断の転載を禁じます。
全ての著作権は株式会社武蔵野種苗園に帰属します。