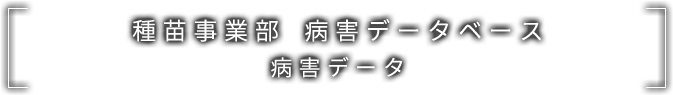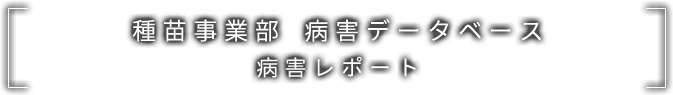キャベツ菌核病
発生の生態
発生の原因
- キャベツ菌核病はかびの一種Sclerotinia sclerotiorum(スクレロチニア・スクレロチオルム)でおこる病気です。
- 菌核病菌は宿主範囲が広くトマト、ナス、キュウリをはじめとした果菜類にも感染します。
- アブラナ科野菜も広く全般的に侵し、特にキャベツは侵され易いです。
病徴
- 初期の病徴は外葉の地面に接する部分が水浸状になり、褐色の病斑ができます。湿度が高いと白い綿毛状の菌糸が生えます。
- 病徴は次第に広がって外葉や球全体を黒褐色に軟腐させますが、軟腐病のような悪臭がありません。
- やがて、黒いネズミの糞のような病原菌の塊を作ります。これを菌核といいます。

伝染方法
- 菌核病は菌核が土壌中で生き残り一次伝染源となります。
- 菌核の大きさは3~15mm程度で、いろいろな形のものができます。菌核はキャベツの結球した表面だけでなく、葉の間や茎の中にもできることがあります。菌核は成熟すると落ちて土壌中で4~6年という長い間生き残ります。
- 菌核病菌が植物に侵入(感染)する方法には2種類あります。
- 1つ目は胞子を飛ばす方法です。菌核は最低気温が10℃前後の日が数日続くと発芽し、小さな茶褐色のキノコのようなもの(子のう盤)を作り広範囲に胞子(子のう胞子)を飛ばします。胞子は古くなった花弁や茎や葉の組織や傷口から侵入し、次第に茎や葉に広がっていきます。
- 2つ目の方法は、菌核から直接菌糸が伸びて植物に侵入する方法です。キャベツやレタス、ハクサイなどでは主にこちらの方法での感染が多く、地面に接している古くった下葉や傷口などから菌糸が侵入します。
発生条件
- 春先や秋に、やや低温で降雨の日が続くと発生が多くなります。
- 菌の生育適温は15~24℃で、子のう胞子の発芽適温は16~28℃、菌核の発芽適温は20℃前後です。
- 菌核病の発生時期は春から初夏ですが、11月から3月頃の発生が多く見られます。3月または9月頃に雨が多く、20℃ぐらいの気温が続くと多発します。
- キャベツでは、夏蒔き秋冬どり栽培で、翌年の2月頃から発生し始めます。暖冬で多雨の年には1~2月に多発することがありますが、普通は3~4月、または4~5月に急増します。
防除のポイント
耕種的防除
- 被害株は早期に抜き取りましょう。
- 夏季に約1ヶ月間の湛水処理で菌核を腐らせることができます。
- 残渣は伝染源となるので圃場に残さず、土中深く埋めるか焼却処分しましょう。
- ポリフィルムによって土壌表面のマルチをしましょう。
- ハウス栽培では、紫外線カットフィルムを張りましょう。
薬剤的防除
- 最新の登録農薬を確認し、使用法に従い正しく使用しましょう。
このページに掲載のイラスト・写真・文章の無断の転載を禁じます。
全ての著作権は株式会社武蔵野種苗園に帰属します。